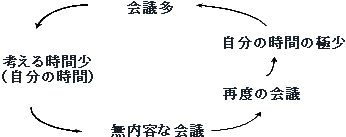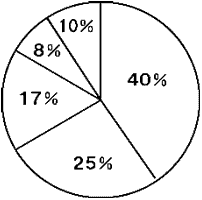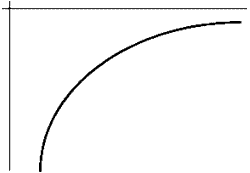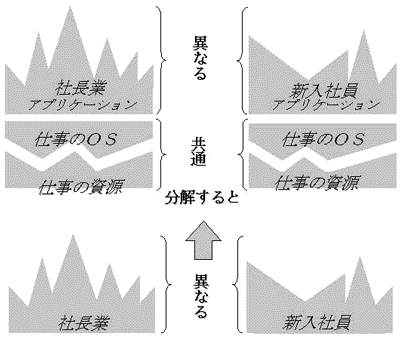| ビジネスコミュニケーションを向上させる連載小説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■□■□ 第一部 ■□■□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 プロローグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月和弘は朝から数えて4回目の会議に参加しながら、辟易としていた。4回目の会議は始まって1時間ほど経ったが、少なくともあと1時間はかかるだろう。会議室の置き時計に目をやると午後6時30分を回ったところだ。望月は心のなかで「あーあ、今日も一日が終わってしまう。」とつぶやいていた。 望月和弘が第2営業部の部長に着任してから6ヶ月が経った。17年前新任課長代理で着任した時は総勢13名だった部も、今回新任部長として着任した時には、130名の大所帯になっていた。この間、会社は急成長をとげ2部上場、1部上場を実現した。現在では業界でも屈指の大会社である。 古巣の部に戻るということもあって、辞令を受取ったときは、多少の不安もあったが、体中にやる気がみなぎって来る感覚を望月和弘は経験した。しかし、着任して6ヶ月が経った時点において、やる気と不安は逆転してしまったようだ。 着任早々、得意先へのあいさつ回りに2ヶ月の時間を要してしまった。2ヶ月の時間を要したのには訳があった。1社あたりの滞在時間が予想に反して長くなったためであった。単なる着任あいさつで終わるケースは稀で、ほとんどの会社で各案件の具体策を話し合うはめとなってしまった。主要取引先を毎日回って1ヶ月で50社を過ぎた頃には、もうヘトヘトになっていた。好きな酒にも、自然と足が遠のき、疲れに拍車がかかってしまったようだ。 景気が悪いせいもあり、各社とも、すがる思いで望月和弘に様々な問題点や、要望を嵐のように持ち掛けてきた。無理難題の山が日1日と高くなるのが良くわかった。 部長昇格を喜んでいられたのは、多分数日だった。得意先を回って、部の問題点が鮮明になり、あれもこれもやらねばと頭はフル回転の状態となった。2ヶ月をかけて、得意先回りが一段落し、「さあ、対策を取るゾ!」と意気込んだ瞬間、思わぬ事件が生じてしまった。直属の上司、担当役員である常務が、株主総会で専務に昇格したのはよかったが、担当役員からはずれ、望月の部は副社長直属ということになってしまった。昇格した専務は望月和弘が課長代理時代の直属の部長で、部の仕事には精通していたし、何よりもかつての上司・部下とういうこともあり、信頼関係もあった。しかし、副社長は銀行の出身で、望月和弘が大阪支店時代に入社して来たこともあり、ほとんど面識もなかった。 株主総会後の1ヶ月は、副社長への状況報告、説明であっという間に過ぎてしまった。望月和弘の部は、会社の中でも、利益を出している数少ない部である。しかも、会社の利益の大半を出している部である。しかし、このままでは、来年度は利益を出せる見込みが現時点ではまるっきりなかった。このことは会社が赤字転落することに直結していた。「何か効果的な具体策をとらねば…」と気はあせっても、なかなか本題に入れない。もどかしい日々が3ヶ月も続いてしまった。 野球のペナントレースではないが、完全にスタートダッシュにつまづいてしまった。こうなってからでは、全てのことが後手後手となり、不必要に仕事が増えるから不思議である。4ヶ月目以降、望月和弘はファイヤーマンと化してしまった。こちらの課で問題が生じれば対策をとり、あちらの課で相談があれば打合わせをし、むこうの課で、やめたい社員がでれば説得し、突然電話が入る得意先からのクレームに対応し、経営会議の前には副社長のレクチャーと仕事をする内に、あっという間に6ヶ月という貴重な時が過ぎていた。 部長会に参加しながら、望月和弘は「このままでは、自分がつぶれてしまう。そして何よりも来年度は赤字転落だ。このままではダメだ。何か新しいことをはじめよう。」と決意を新たにした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 望月和弘部内アンケートを実施する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月和弘は、熟慮の結果、部員にアンケートを取ることにした。東洋の兵法ではないが、「己を知り、敵を知る」という視点でいえば、得意先は回ったが、130名いる部下とは満足に面談もしていないことに気づいたからである。130名を活かす方法を見つけるためにも、また短期間でそれを活かす方法をみつけるためにも、アンケートが1番と判断した。 アンケートを作成、実施するにあたり、現在は経営コンサルタントとして独立しているかつての部下に相談することにした。 アンケートの目的は、自分が精度の高い仕事をするためと決めていたので、コンサルタントにその旨を伝えた。コンサルタントは様々な質問を望月和弘にした。望月はありのままを伝えた。 1)あっという間に6ヶ月が過ぎたが、部長らしい仕事は何1つできていないこと 2)会議ばかりで、何ら仕事がはかどってはいないこと 3)部下がどういう気持ちで仕事に望んでいるかもわからないこと 4)各課、チームでどう仕事が進められているのかわからないこと 5)もっとはっきりいえば、どうも仕事の進め方自体に問題がありそうなことを伝えた。 数日後、コンサルタントからアンケートの素案が提案された。内容は、主に意識調査であった。興味の持てる内容だったので、了解し、せっかくなので、全社で実施するよう段取りを取り、アンケートは実施されることとなった。
望月和弘はこのアンケート結果に大変興味を持った。これは、大変矛盾に満ちている結果である。そもそも、会議はコミュニケーションを良くするために行う1つのシステムである。望月本人も、社内コミュニケーションに問題があるとは認識していたが、アンケート結果でそれが裏付けされた。それも、会議が多いグループの方が、本来の目的であるコミュニケーションが逆に悪いと感じているのである。この現象が生じる原因なり、プロセスが解明できれば、会議についての効果的な対策も、会議のあるべき姿も見えてくるように思えた。 そこで、望月和弘は、自分なりに、このデータに解釈をつけてみることにした。 まず、考えついたのは自分の経験則からいっても「下手くそ」な会議である。本来の目的であるコミュニケーションを実現できない「下手くそ会議」が原因と思われた。 しかし、良く考えると、「下手くそ会議」だからコミュニケーションが悪いのか、それとも、そもそもコミュニケーションそのものが悪いので「下手くそ会議」になるのか。これは重要な問題である。 望月和弘は、熟慮の結果、コミュニケーションが、下手くそだから、「下手くそ会議」も多くなるに違いないと仮説を立てた。経験則でいっても、コミュニケーションが欠如すると打合わせ、会議で何とか、互いの状況を確認しあっている訳だ。上手なコミュニケーションが実現していれば、そもそも会議が増える訳もないし、ましてや「下手くそ会議」がハンランすることもないと思われた。 望月和弘は、アンケートの結果の分析にはまっていた。理由は久々に考える時間が持てたからである。考えれば考えるほど、気分は上々であった。それは、アンケートの目的であった「己を知る」が着実に実現しているからと思われた。自分や会社の実態が良くわかるにつれ、今後何をしなければならないかも、次から次から様々なアイデアが頭の中をかけまわっている。少なくとも、アンケートの分析をするようになってから、暗い気分はなくなり、着任当時の「やる気」が体に充満して来るのが感じられた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 部下とコミュニケーションの関係を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日の分析は、「部下との関係とコミュニケーション」についてである。この調査は会社の課長代理以上500名を対象に行なった。部下を持っている管理職と、コミュニケーションについての関係である。
次に、コミュニケーションの良し悪しとクロスさせると望月の疑問は更に増幅されることとなった。「思い通りにならない部下はいない」とするグループでも、チーム内コミュニケーションが悪いと回答した者が、51%と半数を越していたのである。当然のことだが、「思いどおりにならない部下がいる」とするグループではコミュニケーションが悪いと回答した者は、7割近い数字であった。これは当然としても、「思い通りにならない部下がいない」とするグループの半数がコミュニケーションに問題を抱えているとなるとこれは大きな問題ではないかと望月和弘は思った。 望月が抱いたイメージは、あまり良いものではなかった。何を言われても、「YES」と答える「能面」のような社員の集団をイメージしてしまった。または、部下の真の状況を知らずに、能天気に「思い通りに動いている」と勝手に解釈している管理者の集団もイメージされた。いずれにせよ、これはあまりいいことでないことだけは、確かだった。 コミュニケーションに問題がありながら、管理者の指示通り、イメージ通り、部下が仕事しているとなれば、超優秀な社員の集団か、それとも、実は、「思い通りにうごいている」と管理者が都合よく思っているかのどちらかである。この単純なアンケートの奥深くに流れている「魂」のようなものを望月和弘は感じたような気がした。 このアンケート結果から、望月は、仕事の進め方とか、コミュニケーションが非常にあいまいに取り扱われているのではないかと感じはじめていた。 確かにコミュニケーションという言葉は、日常良く使う。しかし、どうも各自の捉え方がマチマチのようだ。 望月和弘はもっと、実態が知りたくなった。そこで、コンサルタントに電話して、自分の見解を述べてみた。コンサルタントからの返答は、いたってそっけないものだった。 「別に今は、詳細な調査は必要ありません。望月さんが、そういう風に感じたこと自体が重要なことで、それだけでもアンケートの目的は達成できてますよ。」確かにいわれてみれば、そんな気もして来る。今まで、考えてもみなかったことを考えるようになって来ているのは事実だった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 まわりは何を考えている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日1データの分析を独断と偏見ではあるかもしれないが行ってみて、望月の頭の中をあるフレーズがふいに浮かんだ。「何を今さら!!」。ビジネスマンを30年近くもやって来て、それなりの成果も出して来たつもりだが、今やっている作業は、どうもビジネスの基本中の基本のことばかりだ。「何でこのオレが新人研修のテーマみたいなことに没頭しなけりゃならないんだ!?」。しかし、心の中でそう考えても、現実は基本中の基本のデータ分析にハッとすることの連続である。どうも、これは、今までの30年間を根底から見直さなければならないかもしれない。そんな思いも心の中のある部分に発生し、拡大しはじめているのも事実であった。
このデータに、コミュニケーションをクロスさせると、事態はより一層深刻な状態である。目標が不明確と回答した35%のグループの中で、29%の社員はコミュニケーションに問題がないと答えている。全体でみると約10%(35%×29%)の社員は、ほとんど何も考えず、問題意識も持たずに仕事をしていることになるのではないだろうか。 一方、仕事を進める上で重要な項目である目標設定ができていると思われるグループの方が不明確なグループより、コミュニケーションに問題ありとする割合が高い。総数でも、50%:25%で、目標が明確なグループの方がコミュニケーションが悪いと感じる人が倍いる計算となる。常識で考えれば、組織で仕事をしている訳だから、目標が明確であれば、コミュニケーションも良くなるのが道理である。全く不可思議な調査結果である。 望月和弘は、この不可思議なデータを真剣に考えてみた。出た答えは2つあった。一つは良い解釈、もう一つは悪い解釈である。良い解釈では、目標が明確であるために、他人に譲れるところとそうでないところが明確になり、特に譲れないところで相手との衝突、調整が必要となり、それが上手に行かずコミュニケーションが悪いと感じてしまうケース。悪い解釈では、目標は明確ではあるが、その目標自体に問題があるために、衝突、調整が頻繁に発生し、コミュニケーションが悪いと感じてしまうケース。 この2つのケースをまとめると、どうも、コミュニケーション能力も弱く、目標設定能力も弱いと判断するのが妥当であるように望月には感じられた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 右往左往現象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月和弘は、今日は朝からルンルン気分だった。昨日のデータ分析を自画自讃もしていたせいもあるが、1日1件のデータ分析と決め、今日は1番楽しみな優先順位、プライオリティのデータ分析の日でもあったからである。 この6ヶ月は、正に右往左往の日々だった。頭の中では、優先順位、プライオリティはビジネスの基本と理解しているつもりだが、現実の自分の仕事は、いつもその場しのぎ、出たとこ勝負で、優先順位、プライオリティのかけらも感じられないのが実態である。 今日は、じっくりとビジネスの基本を考えるいいチャンスであった。
つまり、データの解釈としては、全社内には業務多忙ではないらしいということである。しかし、クロスしたコミュニケーションの結果を見ると、どうも目標と同様なことが生じているように望月和弘は感じていた。 優先順位が混乱していないグループの方が、コミュニケーションが悪いとする割合が高い。目標と同様の分析をすれば、優先順位のつけ方自体に問題があり、衝突、調整が必要となり、コミュニケーションが悪いと感じるか、または、優先順位が明確なために、相手とのコミュニケーションに問題が生じやすいかのいずれかである。 優先順位が混乱していれば、相手とのコミュニケーションも混乱する。これは、コミュニケーションにすらなっていない可能性も高い。よくいわれる朝令暮改である。しかし、ここでも、優先順位が混乱しているにもかかわらず、コミュニケーションは問題ないとする社員が1割弱(9%)程度いる。どうも我社には能天気社員が全体の1割は確実にいるようだと望月は感じていた。 逆に、優先順位が混乱せず、コミュニケーションも上手に行ってる社員は全体の13%いることになる。美しい仕事をしている社員がそんなにいるか疑問には思うが、とりあえずデータの客観的分析として理解しておくことにしようと望月は思った。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 考える時間がない!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
望月和弘はOA協会の調査資料(図1-5)に目を通していた。
パラパラとめくって、このページに目が釘づけになってしまった。とてもおもしろいデータだと思った。社内データとは異なり、ビジネスマン、サラリーマンの一般的傾向を知ることのできるデータだ。しかし、一般的とはいっても、十分に望月の会社にも共通するように思われた。所詮「人」のやること、業種、業態が異なっても、ベーシックなところでは同じなんだと1人で納得していた。 望月が最初におもしろいと思ったのは、「欲しい時間」は段突で「考える時間」であるが、「いらない時間」はどんぐりの背比べだ。これは非常に興味深い。減らしたい、いらない時間は、困っていること、またはプライオリティの低いことである。それがどんぐりの背比べということは、プライオリティの低いことは人によりマチマチであるということである。 一方、欲しい時間もその時間がなくて困っている訳だが、これは人によりマチマチではない。ほとんど全員共通のようなものだ。4人に3人は考える時間が欲しいのだ。確かにこの資料を見ている望月和弘もその例外ではない。ただ、ここのところアンケート分析が日課になったせいか、以前より考える時間は格段に増えている。気分も上々であった。しかし、このデータを考えると、笑って済まされない状況だ。考える時間が欲しいということは、考える時間がないことに直結する。考える時間がないということは、考えずに仕事をしているも同じだ。または、十分に考えずに中途半端に考えているということだ。 そこで、望月和弘は、あるOA機器のテレビコマーシャルを思い出した。「これさえあれば、あとは何もいらん。あとは考えるだけ。」という携帯情報端末のテレビコマーシャルに妙に触発されて、急にその商品が欲しくなった時を思い出してしまった。今考えてみるとあのコマーシャルを作ったコピーライターも、自分と同じデータを見てコピーを考えたのではないだろうかと望月は思った。 次に望月が共鳴したのは、「食事」の時間だ。自分の仲間が5人に1人はいる計算だ。満足に昼食も取れずに仕事をしている厳しい現実を、古女房にわからせてやりたいものだと多少鼻息が荒くなっていた。 望月和弘は「考える時間」について、もう少し、突っ込んで思案をめぐらせていた。これだけ多くのビジネスマンが考える時間の欠乏病にかかっている。望月はハッとした。考えないで良く仕事が成り立っているものだとしみじみ感じ入ってしまった。そう思うと、急に仕事が成り立っているのか不安になって来た。そして、ギャグ好きの望月は、またもハッとした。「赤信号、みんなで渡れば恐くない」だ、と思わず叫びそうになってしまった。そうだ、みんな考えずに仕事をしているから土俵が同じだ。差がつかないのも当然だ。ちょっと考えれば、アドバンテージが持てる。差別化された仕事ができるんだと思うと目がギラギラと輝いてしまった。 確かに深い洞察に欠ける仕事が往行している。望月自身は断ったのだが、実は、間接部門からの人員応援の打診が人事からあったのだ。昨今の不況の中、現場重視で間接部門から直接部門に人を送り込むのは、どの企業でも行われている。望月の会社もそれにならんで、人事から打診があった訳だ。望月は、現状の部員の管理でさえ、きゅうきゅうとしていたので、これ以上はオーバーワークと断ったのだが、今考えれば、人事の施策に対し、大きな疑問が湧いて来てしまった。「あいつら、考えたのか?!」と望月は思った。単に世の中の流れをマネただけじゃないのか?!知識の乏しい営業がお客様と接することのダメージをどこまで考えたんだ?!確かにお客様と接する時間が増えれば営業成果が上がるように思えるが、それは営業の基本も応用も知っている人間が行った場合のことなのだ。現に、望月のところにも、様々な営業が飛び込みやら、電話やらで、めったやたらと多くなって来ている。しかし、それらの多くは、商品知識も乏しく、営業のイロハも知らずで、腹立たしく思うこともしばしばだ。今思えば、腹立たしいという瞬間的な感情の問題だけではない。もっと恐ろしいのは、望月自身も腹立たしさと同時に、「そんなもん買うか」とか「こんな営業を使っている社長の顔が見たい」とか思っていたのだ。 浅はかな考えは、時によっては命取りにもなるのだと望月はまとめてみることにした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 会議と真剣に向かい合う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コミュニケーションを横軸とした、様々なアンケート分析が一段落し、望月和弘は1つの結論めいたものを持ち始めていた。 自分の経験でもそうだが、今までは「会議ばっかで仕事にならん!!」という状況だった。今でもその状況は何らかわってはいないのだが、アンケート分析をしたことにより、冷静に受け取め、考えることができたことにより、ある種のゆとりが生じたことは事実だった。 どうも、コミュニケーションの技術に根本的な欠陥があるようだ。その具体例、現象として、会議の多さ、空回りがあるのではないかと望月は考えていた。そして、それに対する効果的な具体策も見えはじめていた。コミュニケーションの技術そのものの修得では、あまりにも抽象的、非実戦的だが、会議の技術であれば具体的でかつ実戦的なテーマである。会議を通して、コミュニケーションのスキルアップをはかるのが、自分自身もそして、自分の部も確実にレベルアップすると確信しはじめていた。 座右の書である「セルフマネジメント・スキルBOOK」にも確か書いてあったはずだが、「自分1人の仕事」の時間と「他人と共同の仕事」のバランスが崩れると、生産性は低下する。そんなようなことが書いてあったはずだ。あの理論でいえば、「会議」は「他人と共同の仕事」だし、みんなが欠乏していると感じている「考える時間」は「自分1人の仕事」といえそうだ。 「会議」が多くなって「他人と共同の仕事」ばかりになると、「自分1人の仕事」、特に考える時間は減少することになる。そのため、準備不足や、ぶっつけ本番で、「会議」に参加することとなる。そんな会議は内容もなく、結論もなく、時間の無駄だが、更に悪いことにそんな会議に限って、もう1回やるはめになる。それで、ますます「自分1人」の時間が減少と、悪循環に陥ってしまう。これはもう、生産性低下の「会議の悪魔のサイクル」だと望月は感じていた。そして、それがさほど問題にならないのも良くわかっていた。
望月和弘は自信に満ちていた。これから最優先で取り組むべきテーマがはっきりしたこともあるが、そのテーマを解決したあかつきには、輝かしい未来が待っているのが確信できたことにもよっていた。 自分の多忙や、売上げが減少とは一見、直接的な関係がないと思われがちな会議ではあるが、望月和弘は、これこそが自分の多忙や売上げ減少対策の究極の一策と確信していた。理由は簡単であった。「仕事は自分と他人の共同作業」なのだ。そして、ビジネスにおいて、その自分と他人が直接的に接するのは「会議」・「打ち合わせ」なのだ。この部分のスキルアップが実現すれば、仕事そのものの、精度向上・実績向上につながるのは道理である。 望月和弘は、当り前のことを当り前にやるために、「会議」と真剣に向い合う決意を固めていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 会議プロジェクトチームを結成する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ついに、望月和弘は、自分と部の生産性向上を実現するために、「会議プロジェクトチーム」を結成することに決意した。 全社プロジェクトにすることも考えてみたが、横ヤリや自分のコントロールが効かなくなる可能性もあるので、部内プロジェクトがベストと判断し人選をはじめた。 人選と同時に、進め方についても考えはじめるとあれやこれやとアイデアが浮かび、自分だけでは収拾がつかなくなってしまった。 そこで例のコンサルタントに相談してみることにした。 「望月さん、ついにやりますか。それはすごい。ご相談の人選と進め方について、望月さんの熱意に応えるべく考えましたよ。まず、2つのチームを作ってください。1つは、現役バリバリの中堅社員グループ。もう1つは、次長、課長さんのグループ。そして望月さんは、中堅社員グループに入ってください。中堅社員グループが会議システムの提案を作成し、管理職グループにプレゼンし、管理職グループが承認するというスタイルはいかがですか。社内でTQC活動もおやりだから、お手のものでしょう。多くの副次効果も期待できますよ。」と簡単、明瞭な答が電話をとおして伝わってきた。 さっそく、中堅社員グループの中から、特に多忙な人間を選択し、メンバーには自分の座右の書である例のコンサルタントの著作の中から、仕事のしくみ、原理・原則やチームワークについて書かれているもの2冊を第1回目の会合まで必ず読破するよう指示を出した。しかし、あえて管理職グループにはその指示を出さずにおいた。 ついに第1回目のプロジェクト会議が開催されることとなった。集まったメンバーは、「この忙しい時期にやんなちゃうよ」とか、「どうせ長続きしないんだから、しばしのしんぼうよ」などと口々に好きなことをいっていた。しかし、望月部長が登場すると、さすがに静かになった。 「今日は忙しい中をありがとう。」望月はこのプロジェクトをとおして、部の生産性を向上させることや、できれば会社に新しいシステムを浸透させる予定であることを話した。そして、このプロジェクト会議においては一応議長を務めるが、メンバーと同列であると話した。短期間であったが、メンバー全員、宿題である2冊の本も読み終えていた。 メンバーはフリー討論ということもあり、会議の種類の分類をそれぞれ言いあった。ひととおり発言が終ったところで、あるメンバーが、「今まで、出た分類って、本屋にある会議の本にも出てるよね。それじゃ、つまんないから、もっと違ったのないかなあ」といった。そうすると別のメンバーも「オレも同感。実はさあ、宿題の本の、携帯情報端末のほうかな。「仕事のOS」ってのがあったじゃない。新入社員にも社長にもあてはまるってヤツ。オレあれ気に入っちゃたんだよ。あの発想でさあ、分類すると結構イケルのができるんじゃないかなあ。」この発言をきっかけに、全員でその本の43ページにある表をもとに活発に意見が交わされた。
1. 誰が参加するかで、 1)チーム内会議 と 1)’チーム外会議 2. どう行なわれるかで 2)経続型の会議 と 2)’企画・単発型の会議 3. 何がテーマかで 3)事前にわかる会議 と 3)’突発の会議 4. 必要なノウハウは何かで、 4)調整型の会議 と 4)’専門・技術型の会議 に会議の種類を分類することで合意した。 全員、望月和弘も含め、この分類には満足だった。気に入った1番の点は、他にはなく自分たちのオリジナリティが高いこと。2番目には、会議だけでなく、仕事のしくみ、原理・原則をベースにしているので、あらゆる会議をこの分類で把握することができることであった。例えば、定例のチーム会議は、チーム内で、経続型で、事前にわかって、一般的には調整型の会議ということになる。 これで、このプロジェクトは多分、うまく行くだろうと、全員がウキウキしていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 プロジェクトチームに名前がつく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2回目のプロジェクト会議が開催された。望月和弘は、予定より5分早目に会議室に行くことにした。会議室に着くと、そこにはすでに数名のメンバーが集まっていた。望月が到着して間もなく、他のメンバーも集まり、定刻前に全員がそろってしまった。望月は内心「しめしめ」と思っていた。第1回目は、多忙を理由に、遅刻したものも何名かいたが、今回は定刻前のスタートである。これだけでもメンバーの「やる気」がわかるというものだ。 望月は口を開いた。「じゃ、はじめようか。ところで今日は遅刻ゼロだな」そうするとあるメンバーから「宿題の本を読んで、仕事の進め方のコツがわかりましたから、当然っすよ。」と声がかかり、全員ニヤニヤしている。望月はコンサルタントのアドバイスに心底感謝していた。正しく、中堅どころのガンバッてもらわねばならない層に、早くも副次効果が出ているようだ。 「今日は、会議の目的を討論する予定だけど、せっかくだから、プロジェクトチームの名前をつけないか。」と望月は提案してみた。すかさずメンバー全員から「賛成!!」の声がかかり、全員でチーム名決定のフリー討論がはじまった。 最終的に2つの案に絞られることとなった。1つは「元気のでる会議プロジェクト」。もう1つは「夢現(むげん)プロジェクト」であった。前者は、テレビ番組の影響が大である。後者は、夢が実現と、部が無限大に発展するが掛け合わせれていた。この2つに絞られるまではスムーズに進んだが、最終段階に来て、なかなか意見がまとまらなくなってしまった。望月本人も両案とも捨てがたいと悩んでいた。そんな中、あるメンバーが「両方のいいとこ取りして、『元気君の夢現プロジェクト』ってのはどうだ?!。」といい出した。一瞬の沈黙のあと、大きな拍手がおこり、望月の仕掛けた「会議プロジェクト」は「元気君の夢現プロジェクト」に決定されることとなった。 「さて、いい名前もついたところで、前回の宿題はできたかな。」と望月はいった。 「チーム員からのヒアリングは終ってます。これから、各メンバーのデータを集計します。」と返答があり、前回の宿題であった、各チーム員に対するヒアリング調査「会議の目的は何だ?!」の集計に取りかかることとなった。 その結果は図1-8のようになった。このデータをもとに、全員で討論が始まった。
「考えずに、流されて参加してるってことさ。だからヒアリングして、目的何って聞 いても、『ウーム、何となくかな』ってな感じだよ。」 「わかる、わかる。朝礼とか、定例のチームミーティングなんかは、ほとんどこのパターンだよ。だから、若い連中にこの答が多いんだよ。」 「でも、全体としては、どうやら、会議の究極の目的はコミュニケーションだよね。やっぱり。」 「そりゃ、そうさ。別人格の人間同士が同じ仕事、作業するんだもの。意思疎通を欠いちゃうと重複でやったり、やらなくていいのにやったりと効率も、効果も悪くなるもんな。」 「でも、コミュニケーションって難しいよな。言った言わないでもめたり、勘違いで理解してたり、とても同じ日本語で話し合ってるって思えないことも多いよね。」 「どうやら、元気君の夢現プロジェクト成功の鍵もコミュニケーションにありそうだね。」 「同感、同感。」ということで、改めて、会議の目的はコミュニケーションということを再確認したのであった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 会議のしくみを考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「元気君の夢現プロジェクト」の命名は大成功だった。あっという間に部内はもとより、全社に広まってしまった。部内の他のメンバーも、当初は参加するメンバーに「部長と会議のプロジェクトやるんだって、ご愁傷さま。」なんていっていたのが、「おい、部長と何やってんだよ。おもしろそうだな、仲間に入れろよ。」と大きくマインドチェンジして来た。また、プロジェクトチームからの提案を受ける管理職クラスも『これはウカウカしてられない』とばかりに、密かに書店で会議の本を買っているらしい。先日、望月が帰宅の際、ビル内にある書店で立ち読みしていると、馴染みの店長がやって来て、「望月さん、会社で何かやってるんですか。お宅の課長さん連中、会議関係の本ばかり買って来ますよ。」と耳打ちした。望月は思わず吹き出しそうになってしまった。着任して以来、こんな愉快な気持ちで、部員のことを思い浮かべることはなかった。先日も、たまたま廊下ですれ違った会長から「元気君の部長さん、最近調子はどうかね。」と声をかけられ、苦笑いするしかなかったのだ。望月の仕掛けた「会議プロジェクト」である「元気君の夢現プロジェクト」は確実に前進していた。 今日は第3回目の会議である。テーマは「会議のしくみ」とりわけ「会議のフローを確立する」ことにあった。 例によって、前回の宿題として、全員が持ち寄ることになっていた。望月も例外ではなく、宿題は課されていた。3回目ともなると全員手際が良く、自分の意見を発表しやすいように、環境が整ってくるから大したものだと望月は感心していた。今回は、OHPが用意され、全員、自分の宿題はOHPシートにして持ち寄っていた。各自がOHPで映して説明するスタイルである。 さすがに今回のテーマは、最初から全員の意見はほぼ一致していた。会議のフロー(流れ)は誰が考えても、だいたい同じになるのだ。ただ問題は、そのとおり、実施できているかどうかなのである。 「元気君のプロジェクト」でも 1. 準備 2. 実施 3. フォロー の3つの流れは、全員共通していた。ただ多少の表現方法の違いは当然のごとくあった。それを上記の3つにあっというまにまとめた訳だが、どうも、いつもと違って、会議は盛り上がりに欠けていた。 「なんか、つまんないよな。当たり前すぎて、そう思わない。」 「だって、しょうがないだろう。誰が考えても、この3つだよ。」 「でも、会議のしくみっていう点からいうと確かに物足りないよなあ。おもしろくないよ。今までと違って。」 「じゃ、何か具体的にいってみろよ。」 誰も答えることはできず、しばし、重苦しい沈黙の時が流れることとなってしまった。 その時、メンバーの中では、いつも、みんなに着いて来るような、積極性にかけるかなと思われたメンバーが口を開いた。積極的に発言しない人間が沈黙を破って発言したので、一同は思わず集中した。 「これにさあ、うまく言えないけど『仕事のOS』を応用して、誰がを付け加えると会議のしくみもわかるような気がするんだけど、、、。」 「えっ、どんな風に。」思わず全員聞き返していた。 「会議に誰が参加しているかを考えればさあ、会議を開きたい人と、それに呼ばれる人の2つに別けられると思うんだ。それぞれに、準備・実施・フォローってあると思うんだよね。こんな風にさ。」といいながらホワイトボードに図1-9を書きはじめた。
「あんたは、エライ。そのとおり。主催者と参加者に別けたことによって、準備・実施・フォローのポイントが鮮明だよ。やった、やった。」 「当たり前に当たり前をかけたら、ブレークスルーしちゃったよ。どうも大事なこと忘れてたね。当たり前はこれだから恐いよ。」 という訳で、今回のテーマも無事クリアすることができた。 そんな中で、望月は、鳥肌が立っていた。一番力がないと思われたメンバーが、ブレークスルーしてくれた。うれしい思いと、このプロジェクトをやって良かったとつくづく感じていた。 望月の部は、徐々にではあるが確実に変わりはじめていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 会議の生産性を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不思議というか、恐ろしいというか、「元気君の夢現プロジェクト」はいまだ何等の具体策も提案していないのだが、望月の部ではやれコミュニケーションがどうだとか、生産性はどうだとかの議論が日常業務の中で、ひんぱんに聞こえるようになっていた。 その原因は、プロジェクトメンバーが宿題をチームに持ち帰ることにより、自然とプロジェクトチームの雰囲気が部内に浸透しだしたのと、プロジェクトチームからの提案の日が近づくにつれ、課長クラスも独自に、このテーマに取り組んでいるせいか、日々の仕事の中でOJTとして、部下を指導しだしているせいのようだと望月は分析していた。 コンサルタントが何気なく、2つのグループを提案し、管理職のグループは提案を聞き了承するしくみに、当初は多少の不安もあったのだが、ここまで、うまくはまり、かつ、様々な副次効果が、具体策を出す前に生じるとは望月は夢にも思っていなかった。 別にデータを取っている訳ではないが、このプロジェクトがはじまって以来、得意先からのダイレクトコールやクレームは確実に減少していた。望月は、自分が目指していた、部長らしい仕事ができるようになりはじめていた。それは事後処理のファイヤーマンではなく、事前処理の水先案内人のイメージである。 第4回目のテーマは「会議の生産性」についてであった。 今回も、いつもと同様にこのテーマが宿題で、各自が自分の見解を持ち寄ることになっていた。 前回の会議とはうって変わって様々な意見が提出された。 「会議の時間コストっていうことを考えるとおもしろいよ。不況でも経費節減、経費節減ってうるさいけど、1人1人の生産性ってあんまり考えられていないじゃない。例えば、時間給を算出して、年間の無駄会議の時間を算出して、参加した人数でかければ、それは多分、やれコピー節約だとか、うんぬんなんかに比べものにならない金額になるんじゃないかなあ。」 「それある雑誌で、例のコンサルタントが書いていたけど、年収500万円の社員で、モロモロの諸経費まで含めて、人件費コストとして年間1000万円。「仕事のOS」を知らないで仕事をやると当然、ムダが多くなって、データが出てたけど20%だって。そうすると1人あたり200万円のムダ投資してることになるって書いてあったよ。」 「生産性を考えるのは、今のしくみじゃ、部とか課とか、会社とかの組織単位だけど、それってもとは、オレたち1人1人の集積だよね。そこから考えなきゃ、見えてこないのが現実だよね。」 「会議だって、多勢でやるのあるじゃない、実際、参加してみて、この会議オレいなくてもいいんじゃないっての多いよね。これもやっぱり組織把握っていうか。とんでもないムダやってんだよね。」 「参加している全員が、この会議にはオレは必要ないって感じてたりして。」 「冗談じゃなくて、ありえるよ。」 なんて話しをしながら、会議の生産性を全員でまとめることになった。 様々な議論のあと、生産性だから格調高く方程式にしようという意見が出され、図1-10のような、「元気君の夢現プロジェクト−会議の方程式」が完成した。
この間、望月はだまって聞きいっていた。メンバーがどんどん展開し、方程式まで、作ってしまった。 完成した方程式を見て、望月は、目からウロコが落ちる思いだった。 会議ばかりで仕事にならないので、極力1つの会議で何でも済まそうと対策をとって来た。しかし、「仕事のOS」をベースに考えて行くと、会議は目的別に小人数で数多く行なうほうが生産性が高く、ムダがなくなるというこの結論は、ノーベル賞ものの発見だと、自分の部下を誇らしげに思っていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 会議の投下時間を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「元気君の夢現プロジェクト」は、会議の哲学を十分に行なった。会議の種類、会議の目的、会議のフロー、そして会議の生産性とプロジェクトチーム独自の見解をまとめることができた。望月もこの討論には大変満足だった。会議というどこにでもあって、誰もが行なっている組織維持のシステムが、従来のブラックボックスから徐々にそのしくみが見え出していた。 「元気君の夢現プロジェクト」で、今後の具体策を策定するにあたって、今までの討論をベースに、部内での会議の実態調査を行なうこととなった。 今回のプロジェクト会議のテーマは、投下時間のデータの分析である。
「オレ達は、管理職じゃないけど、会議・打合せが24%ってことはないよなあ。」 「このデータは、全社員だから新入社員も補佐役の女子社員も入ってるし、営業と人事・総務の間接部門との違いもあるからね。」 「そうそう、それに、商談とか、電話対応も入ってないから。」 「そう考えると、ウチの部で、コミュニケーションに投下してる時間て、どれくらいあるんだろう。」 「例のコンサルタントがいってたけど、少ない日で40%、多い日になると80%を越すのがのが一般的だって。」 「そうだよね。それくらいはあると思うよ。」 「最近、不景気で社内研修も少ないけど、コミュニケーションスキルの研修なんか、真剣にやる必要あるんじゃないの。1日の半分以上にかかわってるスキルなんだから。」 「研修っていえばさ、先日大学の同期の飲み会があったんだ。そこでさ、外資系のコンピューター関連の会社に行っているヤツがね、研修、研修でフラフラだってグチこぼしてるんだよ。それで話しを聞いたら、ヤンなっちゃった。年間60時間がMUSTだっていうんだよ。 去年のオレなんか、10時間もなしだよ。日本のコンピューター業界が外資系に勝てないのもわかるような気がしたね。日本じゃ不景気だからって、経費節減するのはいいけど、削っちゃいけないものまで削ってるよね。」 「ある大手の会計事務所のデータに、投資と企業発展っていうのがあってさ、今までの過去の例を沢山だして、研究開発費、人材育成費が減り出すと、数年後には、その会社の業績が確実に低下するってのがあったよ。」 「おい、おい、ウチの会社ダイジョウブか?」 「最近、人事は研修ケチってるけど、ホラ、オレ達が、会議をベースとして、80%はあるかもしれないコミュニケーションの研究やってるし、このプロジェクトだって、人事の研修より、はるかにタメになるから、ダイジョウブだよ。」 「そうだなあ。」 など、多少脱線気味になりながらも、データの討論は続いた。 「しかし、このデータと今までのプロジェクトの成果を併せて考えると、恐ろしくないかい。」とあるメンバーが言い出した。 「どうして?」 「だって、管理職が会議だけで60%だろう。そして、どうもその会議は無駄が多いわけだよね。管理職はハイコスト、会議の無駄が多くなれば、それだけコストが無駄になる可能性も高いじゃん。おまけに、会議の悪魔のサイクルを考えれば、考えなくちゃいけない管理職が考える時間がますます足りない訳じゃん。そうすると、オレ達への適切な指示も出せなくなって、それは、会議への無駄コストの投下じゃ済まないんじゃないの。」 「その意見って、自分が上手く仕事ができないのは、上司が会議ばっかやってるからって聞こえるけど、、、、。」 「まじめに聞いてくれよ。」 「ワリィ、ワリィ、でも、ちょっとは思うでしょう。」 「ちょっとはね。」 望月和弘は、メンバーのフリー討論を聞きながら、今まで漠然としていたものが、一気にクリアになったように思った。 「会議ばかりで仕事にならん」と思っていたのは、部下への効果的な指示などができていない実態へのあせりだったのだと痛感していた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 生産性の阻害要素を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「元気君の夢現プロジェクト」では、会議の実態調査と同時に、生産性についての調査も行なった。行なった理由は、会議の具体策もつまるところは生産性の問題だと認識していたからである。 図1−12は、その結果である。
「いや、やっぱりって感じだね。生産性阻害要素のチャンピオンは会議だ。」 「ジョーダン言ってる場合じゃないゾ!!会議ってのは生産性向上のためのシステムなんだよ。それが阻害要素の1位になってんだもん、ウチの会社は生産性が最低ですっていうデータだよ、これは。」 「そう深刻になりなさんな。ウチの会社だけじゃないから。ヨソもおなじだよ。ヨソが気づかないうちに、こっそり、ウチだけ会議の改革やればいいのさ。」 「しかし、阻害要素ってのは、ずい分あるね。これじゃ、まともに仕事が進まないのも当たり前っていえば当たり前だよね。」 調査にあたって、メンバーが思いつくかぎりの生産性阻害要素を列挙し、複数回答可でアンケートを行なったのだが、中には、前項目にチェックをした回答者もかなり存在していた。 望月は、このデータを見て、ハッとした。重要なあることに気づいたのである。そこで、メンバーに質問してみた。 「このデータを『仕事のOS』の考え方で分析してみて、感じたことを述べてくれないかな。」突発の質問だったので、5分間の検討時間を設けることにした。各メンバーは、データを見つめながら真剣に考え出していた。5分が経過した。 「クレームや専門知識って回答もあるけど、ほとんどが仕事の進め方の問題じゃないですか。」望月からの質問なので、急にヨソ行きの回答である。 「いつものつもりで答えていいよ。」と望月はリラックスするようにうながした。 「阻害要素の1位は、会議だけど、それ以外の上位は、全部個人の問題じゃないかな。仕事のOSでいえば、1位の会議は他人と共同の仕事だけど、それ以外は基本的にはセルフマネジメントの問題だよ。」とあるメンバーがいった。 「あ、なるほどね。」と他のメンバーも口にした。 「オレもそう思う。それとさ、何となくだけど、会議とセルフマネジメントの関係が見えるような気もするんだよなあ。」 「どういうことさ?」 「うまく、言えないけど、確かに会議は1位だけど、会議が阻害要素の1位になる背景っていうか、原因っていうのがあってね、それが、会議以外の上位の阻害要素と関係があるんじゃないかなって気がするわけ。」 「それって、こういうこと。会議が阻害要素の1位になるのは、セルフマネジメントがまずい結果っていうこと。」 「そういうことになるかな。会議はビジネスにおいて、悪モノじゃないじゃない。逆にぜひ必要なモノでしょう。それが悪モノの1番みたくなっちゃうのは、会議に参加してる各自が悪いんじゃないの。」 「いえてるよ。それ!!セルフマネジメントが上手にできてないから、会議が結果として、阻害要素みたいになっちゃうんだよ。だって、自分一人で仕事もやってる分には、セルフマネジメントが良かろうが悪かろうが関係ないじゃない。だけど、会議みたいに他人と共同の作業において、各参加者のセルフマネジメントが悪いと、悪の相乗効果っていうかとんでもなく生産性が悪くなるんじゃないのかなあ。」 「会議のフローでいえば、主催者も参加者も事前準備が上手に行かないってのは、このセルフマネジメントに課題があるんだよ。事前準備で失敗すると、その会議事態アウトだよ。そんな会議は正しく生産性の阻害要素になっちゃうよ。」 「会議の具体策が見えましたねえ。セルフマネジメントの充実だあ。」 「同感、同感。」 「部長、こんな結論でいかがですか。」 望月は満足していた。質問を投げかけるだけで、ことの核心をつく回答を導き出したメンバーに心の中で拍手をおくっていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 節約可能時間を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「元気君の夢現プロジェクト」では、生産性の指標として時間コストを軸にする考え方を持っていた。そこで実態調査でも、各自の仕事において、どうすれば、時間コストが低減できるかを調べてみることにした。 図1-13は、その調査結果であった。1位は会議を上手にやれば25%の時間が節約可能であるという調査対象者の見解である。ここでも、やはり1位に会議が来てしまった。
「それってのは、逆をいえば現在20%のムダやってますってことだよね。」 「そういうこと。だから、例のコンサルタントも、年間200万円の無駄経費だっていうんだよね。でもさ、この200万円良く考えると大変だよ。」 「良く考えなくても大変です。」 「茶化さないでくれよ。日本での就業人口って6000万人位いるわけでしょう。200万円×6000万人っていくらになると思う。120兆円だよ。考え方によっては、この国全体で、年間120兆円のムダ投資してることになっちゃうよ。この金額があればさ、今問題の不良債権も一気にケリがつくのにね。」 「このプロジェクトは、国家的改革の会議ではありません。脱線しないように。」 「でも、事実だよね。少なくとも、ウチの部だけでも、効果的な対策を策定できるようにガンバリましょう。」 「しかし、ここでも会議が1番だね。」 「本当。これは、会議の時間そのものもあるけど、会議を上手にやることによって、その後に節約できる時間も入ってるんだよね。」 「回答者がどんな風に考えたか、知らないけど、そこまで入れたら、25%じゃ済まないような気がするな、ぼくは。」 「同感。上手くやれば1回で済むのに、何回もやる会議とか、日常業務を上手にやっていればやらなくていい会議とか、たくさんあるよ。」 「たしかに。でもね、このデータを見ててさ、前回の会議と同じようなことがいえる気がしないかい?」 「どういうこと」 「セルフマネジメントっていうか、仕事の進め方っていうか。確かに、会議は25%でトップだけどさ、どうやら、セルフマネジメントがキーポイントって感じするね。確信に近い状態になっちゃたよ。これ見て。」 「でもさ、確かにセルフマネジメントは大事だっての良くわかるけど、会議とか、委任とか、情報共有化ってのは1人じゃできないことだよ。相手がいないとできないよ、これは。」 「たしかに。」と全員うなづき、どうやら壁にブチあたったようであった。 しばらくの沈黙のあと、あるメンバーが例のコンサルタントの著作をパラパラめくりながら発言した。 「この本の98ページを見てよ。トップダウンとボトムアップの図があるじゃない。これヒントだと思うな。」 「どれどれ」と全員そのページをめくった。 「あれ、99ページの図は、ウチのプロジェクトチームのシンボルマークだ。無限マークだよ、これは。」 「ホントだ。トップダウンとボトムアップが循環すると無限マークになるんだ。なるほど。」 「仕事において、時間を節約するってのは、各自の努力と組織・チームの努力と両方が合体した時に成果が出るんだよ。きっと。」 「そうか、会議とか、情報の共有化ってのは、この個人とチーム・組織の接点なんだよ。接点だから両方のしくみが必要なんだよ。個人のシステムがセルフマネジメントで、組織のシステムがルールとか決まりとかなんかなんだと思うな。」 「会議のシステム作るにも、この両方の視点が必要ってわけだ。やあ、今日も実り多い討議ですなあ。」 メンバーがどんどん話しを進めるのを、望月は黙って聞き入っていた。そして、セルフマネジメントはメンバーにガンバってもらうにしても、もう一方の組織のしくみ、ルールこそ、自分の担当分野だと感じていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 会議の達成度合を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議の生産性を検討するのに、投下時間という考え方ともう1つ達成度合という考え方がある。達成度合とは、その会議の目的が達成実現されたかどうかの問題である。 「元気君の夢現プロジェクト」では、この会議の達成度合についても、アンケート調査を行なった。 結果は図1-14のとおりであった。
「どれどれ、ほんとだ。こりゃあ、おもしろい。」 「他人がかかわる割合が多くなると、急激に達成度が低下するんだ。」 「オレ達のつくった会議の方程式の裏付にもなるね、このグラフは。」 「でも優先順位が高いっていうか、大事というか、重要っていうか、そういう会議になればばるほど達成度が低いってのは、大変なことだよ。パレートの2割8割の法則じゃないけど、どうやら、そもそも生産性向上ができない環境にいるみたいだね。」 「生産性低下は環境の問題かあ。でも環境の問題って都合のいいフレーズだね。さも、オレ達には問題がないみたいだもの。」 「そういう意味じゃなくてさ、望月部長がよく言ってる『赤信号みんなで渡れば恐くない』って意味での環境さ。」 「確かに、いつもやってるからって、いつもどおりにやることの恐ろしさってのがあるよね。深く、良く考えれば、どうしてこんな不合理なことやってるのって、オレ達のビジネスの中には山ほどあるよ。」 「この会議のデータだって、そうだよ、他人との意見の刷り合わせが必要になれば、なるほど達成度が低くなるってのは、ちょっと考えればわかることだけど、こうやって調査してデータにして、はじめて、『あ!!そうなんだ』ってわかる情けなさってのがあるね。」 「オレ達の場合は会議の生産性について、あれやこれや検討して来たから、このデータは重要だって思うけど、そうでない人に見せたら『こんなのあたりまえ』ですまされちゃうかもしれないよ。」 「いや、そうすまして来たから、会議の生産性なり、ホワイトカラーの生産性ってのが一向に改善されていないと思うな。」 「でも、これで会議の生産性を上げる方向性も見えて来たよね。他人との調整。やっぱりコミュニケーションの問題だよ。」 「そう考えるとさ、報告は達成感が高い結果になってるけど、ホントはどうなんだろう?!一方的に言いたいことだけ言って、終ったら達成度100%なんてのがまかりとおっていたら、それも問題だよ。」 「その可能性は高いような気がするな。相手がどこまで理解したかまで、チェックしながら報告してないもの、私の場合は。」 「いずれにしても、他人、相手との調整、コミュニケーションが重要なことだけは変わらないね。」 様々な意見が出たが、会議の問題は、会議以前の様々な問題の集大成ではないかということで、全員の見解はまとまっていった。 望月は、そこでメンバーにある提案をおこなった。 「このプロジェクトは、会議の生産性を向上させるのが目的だけど、どうも会議以前にクリアしなければならない基本的課題があるように思う。例えば、コミュニケーションとか仕事の進め方とか。そこで、具体案を検討する前に、みんなで、そのあたりの勉強をしてみないか。」 「賛成、ぜひとも。外資系の企業に負けないぐらい、勉強しましょう。」 ということになった |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 悪い会議を考える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月和弘は、「元気君の夢現プロジェクト」でまとめたデータを見ていた。 このプロジェクトが始まって、2ヶ月になろうとしている。望月はこのプロジェクトをとおして、「あたり前の重要さと、あたり前の恐ろしさ」を痛感していた。あたり前の重要さは、別の言葉でいえば基本の重要さということができるかもしれない。新入社員研修で、あいさつの仕方とか、電話の取り方とか、名刺の出し方などをやっているが、それも、もちろんビジネスの基本ではあるが、そういうものではなく、仕事の進め方自体に基本があると感じていた。また、あたり前の恐ろしさは、常識と思っているものの中にある不合理である。どうも、これも仕事の進め方の基本を見失った時、または考えない時に生じているように思えた。 図1-15は、部内の各チーム会議でのヒアリングアンケートの集計結果である。プロジェクトチームのメンバーがチーム会議で、時間をもらい、各チーム員が感じている悪い会議を発言してもらい、それをプロジェクトチームで集計したものである。 プロジェクトチームで作成した、会議のフローと重ねあわせると、「やっぱり」という実感が望月に生じていた。 意識する、しないにかかわらず、会議のフローは誰もがわかっているのだと望月は思った。ただ、それを実行していないだけなのだ。会議の生産性向上のために、会議のフローを実務で定着する「しくみ」をつくるのが部長としての自分の重要な役割だと感じていた。
それは、全てのことに共通しているように思えて来た。全てにおいて準備不足で、いつも「出たとこ勝負」の仕事の進め方が連想、イメージされた。これは、会議の生産性だけではなく、仕事の生産性においてゆゆしき問題であると望月は、事の重大さにお先が真暗になりそうになった。 以下の、中断、進行のまずさ、やりっぱなし、結論があいまいも、こうして見ると、これはどうも会議だけに限ったことではないようだ。全ての仕事に共通しているのではないかと望月は考えていた。 例のコンサルタントが「仕事のOS」という考え方で、全ての業種、業態にあてはまる仕事の原理、原則を説いているが、それは、業種、業態だけでなく、全ての仕事、例えば、会議やら、書類作成やら、商談やらにもあてはまるのだと望月の頭の中で、ひらめくものがあった。 それは、望月のこの会議プロジェクトの成功の鍵のようにも思われた。会議の生産性向上のシステムなり、しくみは、会議だけにとどまらず全ての仕事に応用ができるはずである。会議の生産性向上が実現する時、望月の部は、部の業績自体も向上していることを、暗示する仮説でもあった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 やる気を科学する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
望月和弘は、図1-16のデータを見ながら、ニヤニヤしていた。終に、当プロジェクトの目的地がはっきりしたからであった。
「やる気」という言葉は、精神論、根性論の世界の言葉であると一般的には思われている。しかし、今の望月にとって、この「やる気」という言葉は、限りなく論理の世界の言葉になっていた。もちろん「やる気」そのものは、人間の心の問題だから、精神、根性の問題といってもいいのだが、「元気君の夢現プロジェクト」での様々な討論をベースに考えれば、もっとドライに考えることができるようだと望月は思った。 「やる気」は会議の方程式の「明瞭性」に関係している。つまり、行動計画に直結している問題だと望月は感じていた。行動計画が不明確では、いくら「やる気」を出そうと思っても、その対象がファジーだから、その「やる気」は決して長続きはしない。いずれ尻すぼみになるのは目に見えている。逆に、行動計画が明確になっていれば、「やる気」も常にはっきりし、それに対処するための「やる気」も維持できるはずである。 ただ、「やる気」が実現不可能な場合は、逆効果になるから、その意味でも行動計画の策定には、特別なスキルが必要になるように思える。しかし、行動計画策定のスキルを身につけている部員はどれほどいるか、はなはだ疑問であった。 どうも、会議の問題をやっつけるには、それの前提として、行動計画策定のスキルもそうだが、仕事の進め方の基本スキルをどうしても押さえておく必要性がありそうだ。プロジェクトチームでも、セルフマネジメントの重要性が再三にわたって議論されたことも考え併せれば、仕事の進め方、セルフマネジメントスキルの修得は、緊急の課題のように思えてきた。 しかし、この「やる気」の問題もさることながら、このデータを見ながら、望月は、ほとほと会議というシステムはナーバスだと感じていた。否定的なイメージと、肯定的なイメージは、正しく、コインの裏表である。そう考えると、会議というのは、仕事を上手に進めるか、下手くそに進めるかの分水嶺のようなものだと望月は思った。 山の峯を歩行していて、右の崖に落ちれば下手くそ仕事に、左側に落ちれば上手な仕事になる、その境界をフラフラしながら歩いている。そして、どうも、下手くそ側に落ちるのが一般的なようだ。それは、どうも、容易だからと思えた。誰にでも、何もしなくても、簡単に行なえるから、みんなでそっちに、ついつい行ってしまっているだけのような気がしていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 仕事のOS勉強会を実施する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 望月の部で、「元気君の夢現プロジェクト」主催の「仕事のOS」勉強会が開催されることになった。 開催されることになった理由は2つあった。1つは、プロジェクトチームが会議の具体策を策定するにあたって、仕事のしくみ、原理・原則からアプローチをしようと意図したこと。もう1つは、どうも会議以前の仕事の進め方からアプローチしないと効果が出せないと判断したことであった。後者の理由により、この勉強会には、課長代理以上がとりあえず参加することになった。例のコンサルタントを招聘し、勉強会は始まった。 コンサルタント「さて、仕事のOSの勉強会の前に、皆さんに質問があります。みなさんの会社では、仕事を進める上での様々な取組みをしてらっしゃると思います。例えばフレックスタイムだとか、今はやりのリエンジニアリングだとかですが、それらの取り組みは成果を出していますか。」 参加者「はっきりいって、成果は出ていませんし、途中で消えてしまう取り組みもあります。」とある課長が言い、全員うなずいている。 コンサルタント「では、その原因はどこにあるか考えてみましょう。」ということで各自、自分の意見をまとめ、発表することとなった。「元気君の夢現プロジェクト」の影響で部全体が活性化していることと、管理職にとっては、またとない機会でもあったので、活発な意見が交わされた。 コンサルタント「なかなか、活発な意見が出て、良いですね。私なりに、みなさんの意見をまとめると、こんな風になります。」とOHPに1枚のシート(図1-17)を映し出した。
望月「私も、その意見に賛成です。上手に仕事が進まないのは、ウチだけの特殊事情ということで、納めたくなる訳で、実はその考え方でいるといつまでたっても、ウチは特殊だからで片づけて、何の改善も、進歩もない世界に入っちゃうんですよね。」 コンサルタント「おっしゃるとおり。ではOHPの説明をしましょう。様々な取り組み、今回の望月さんのところでは、会議の改善というテーマですが、それらが上手くいかない、成果の出ない理由は、3つにまとめられます。これは、どこの企業、チームでも同じです。まず『仕事の進め方がマチマチ』。この勉強会に参加している方も、それぞれ個性もあって、仕事の進め方が違います。例えば、優先順位という考え方がありますが、これも、各自バラバラのはずです。この勉強会が何よりも大事だという人もあれば、こんな勉強会出るくらいなら、現場の仕事をしたほうがましだって感じる人まで様々です。これは、今はやりのコンピューターで語れば、分かりやすいと思います。マックのOS、IBMのOS/2、そして人気のウインドウズと、異なるOSのマシンをただつないでも、互いのデータは移せません。つまり、コミュニケーションができない訳です。実は、これと同じ現象が私たちの仕事でも生じているということです。」 参加者「それって、金太郎飴で仕事をしろってことですか。」 コンサルタント「大変いい質問です。全員が金太郎飴のように、全て同じにやるんだったら、人間じゃなくそれこそ機械にやらせたほうが、はるかに生産性は高いはずです。ここでいいたいのは、各自の個性を活かしながら、共通の言葉で仕事をしましょうということです。」 参加者「安心しました。」 コンサルタント「2番目は切実な問題です。様々な取り組みは、現状の仕事にプラスされて行われるのが一般的です。現状の仕事にきゅうきゅうとしていると、その取り組みを行なう物理的、精神的ゆとりがありません。結果として、そのとりくみに各自が無意識のうちに、ブレーキを踏むことになってしまいます。これでは、上手くいきません。3番目は、取り組み自体に問題がある場合です。仕事のしくみを知らず、考えずに、流行や、他社の真似で行なうケースです。成果が出ない理由は、この3点に集約できます。そして、この3点は、今回の勉強会のテーマである「仕事のOS」に直結した問題です。」 参加者「どう直結しているんですか。」 コンサルタント「またまた、いい質問ですね。お話しましょう。「仕事のOS」と「マネジメントスペクトル」の2つの理論(図1-17-b)を理解することによって、仕事の進め方の原理・原則を共通に認識できます。これが個性を活かしながら、仕事の進め方の基本的な部分を共通にすることにつながります。またこの知識を駆使することにより、1日平均20%の時間を創り出すことができます。これは、ブレーキを踏む状態をアクセルを踏む状態に変えてくれます。さらに、この知識があれば、どういう対策が効果的かの判断もできる訳です。ご理解いただけますか。あとは、具体的なスキルをお伝えしていくなかで『あ、そういうこと』と理解していただけると思います。」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 タイムマネジメントを勉強する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回の勉強会は、「仕事のOS」と「マネジメントスペクトル」の考え方をもとに、セルフマネジメントを形づくる3つのスキルについて行なわれた。 コンサルタント「それでは、セルフマネジメントの基本中の基本であるタイムマネジメントについて、勉強して行きましょう。みなさんの中で、時間が足りなくて困っている方、ちょっと挙手ねがいます。」 全員が挙手している。 コンサルタント「時間の問題は、現在ビジネスマンにとって、とても重要な課題です。国際化、情報化が進むにつれ、この時間の問題が注目を集め始めています。時間の使い方、活用方法を紹介した書籍だけでも、ゆうに100冊はありますし、昨今の経営書、ビジネス書や、様々なコンサルタントの方々のお話にも、時間競争とかスピードアップとかが必ず語られるようになりました。しかし、残念ながら効果的な具体策を紹介したものはありません。今日は、「仕事のOS」と「マネジメントスペクトル」の2つの考え方を合体させて、簡単明瞭に、このタイムマネジメントを説明したいと思います。」 「難しくありませんか。」とある課長代理が質問した。 コンサルタント「ええ、ちっとも、難しくありません。ほら、これ1枚で説明がついちゃいます。」といって、OHPを映し出した。(図1−18)
「ホントにこれだけですか。タイムマネジメントって。私も、何冊かタイムマネジメントの本を読みましたが、1冊の本になってましたよ。200ページくらいはあった。」 と、次長が質問した。 コンサルタント「次長さん、その本読んで、タイムマネジメントについて理解できましたか、いかがですか。」 次長「一つ一つのテクニックには、なるほどと、うなずけたのですが、1冊読み終わって、タイムマネジメントって何だって考えると、読む前と同じ「時間管理」ってなっちゃいましたし、逆に混乱して、整理がつかなくなっちゃいました。タイトルには「整理」って字が入ってたんですがね。」参加者から笑いがもれだした。 コンサルタント「物理学にエントロピーという概念があります。乱暴な言い方になりますが、これは、ほうっておくと世の中は、整理された状態からゴチャゴャの状態に向かって進ってことなんですよね。ですから、みなさんの机の上がゴチャゴチャになるのも実は、物理法則にのっとっている訳です。」 参加者「なんだ、要するにあたり前のことなんですね。安心した。」 コンサルタント「安心してもらっちゃ困ります。実は、人間の様々な活動、特に知的な作業はこのエントロピーの逆を行なっているケースが多いんです。みなさんの会議プロジェクトも無法地帯のようなゴチャゴチャした訳のわかんない状態から整然とした生産性の高い会議にしようってんですから、エントロピーの逆ですよね。つまり、人間の知恵でこのエントロピーに立ち向かう訳ですよね。」 参加者「じゃ、机の上がゴチャゴチャしてるのは、知恵のない証拠ですね。」 コンサルタント「一概にそうとはいえませんが、その可能性は高いでしょうね。それで、タイムマネジメントについても同じ、200ページの本でゴチャゴャしてるより、1枚のシートにまとまっている、つまり、知恵の結晶ですから、少なくとも、その1冊の本より価値は高い訳ですね。でも、現実はゴチャゴチャしてる方がお金になる。この1枚のシートを1000円出して買う人が誰もいない。結局、これを必死にまとめた私たちは、いつまでも金欠病ということになる訳です。グチはこれくらいにして、本題ですが、いいですか。」 参加者「じっくり聞きます。」 コンサルタント「仕事のOSから誰が仕事をするかで考えると、この『自分1人』と『他人と共同』の2つになります。またマネジメントスペクトルから考えると、投下時間は『開始(はじめ)』と『期限(おわり)』の2つになります。この2つの要素を組み合わせると、全てのビジネス時間が把握できます。おわかりいただけますか、その時間は全部で4つです。望月さん、その4つを答えていただけますか。」 望月「自分一人の仕事のはじめとおわり、それと他人と共同の仕事のはじめとおわりの4つですね。」 コンサルタント「はい、そのとおりです。この4つしかありません。タイムマネジメントとは、この4つの時間をコントロールすることなんです。次長さん、やれてますか。」 次長「いやあ、他人と共同の仕事のはじめは意識してますが、あとは、今言われるまで気にした事もありませんでしたよ。うーん、なるほど、なるほど。」 コンサルタント「もう、おわかりですね。時間欠乏症になったり、仕事が上手に進まないのは、4つのうちの1つかせいぜい2つくらいしかコントロールしていないせいなんですね。でも、この4つの中で1番大切なのは、何かを知っていることは重要です。4つコントロールできなくても、大切なものをコントロールできてれば今よりは良くなるでしょう。それは、自分1人のはじめです。」 などと、タイムマネジメントの考え方と、具体的なスキルが紹介されていった。(詳しくは、拙著を参考にするか、セミナー受講のこと) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 プランニングを勉強する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムマネジメントの次はプランニングのセッションであった。 望月は、勉強会に参加しながら、スキルを本で読むのと、こうして直に聞くことの違いをしみじみと感じていた。内容的には、本を読むのも、セミナーを聞くのも同じなのだが、理解度が全然違っていた。当然、セミナーの方が、はるかに理解できた。そこで、セミナー中ではあったが、コンサルタントに質問してみた。 コンサルタント「いい質問です。今日の勉強会は、セルフマネジメントの3つのスキルをお伝えしますが、今の望月部長のご質問は、実はコミュニケーションスキルの問題です。本来であれば別料金ですが、サービスでお教えしましょう。」 望月「よろしくお願いします。」 コンサルタント「効果的で上手なコミュニケーションにはポイントがあります。それは主観と客観のバランスにあります。書籍の場合は、筆者の一方的なバランスで展開される事になりますが、このようなセミナーの場合は、講師が参加者の方の様子を見ながら適時そのバランスを変動させることができます。それに、参加者は質問も適時できます。今はやりの言葉で言えば、インタラクティブ(双方向性)ということになります。」 望月「ありがとうございました。ポイントは主客のバランスですね。」 コンサルタント「そのとおりです。一度、チャンスがあれば、このことについても勉強会をおやりになったらいかがですか。いつでも協力しますよ。それでは、このセッションのテーマである、プランニングマネジメントについて、お話しましょう。」 望月「よろしくお願いします。」 コンサルタント「プランニングでも、タイムマネジメントと同様に、仕事のOSとマネジメントスペクトルを用いると、一枚のシートで説明することができます。それがこの図です。(図1−19)」
コンサルタント「ホントに素晴らしい質問です。今日の勉強会は1日なので、典型例で説明していますが、ウチのノウハウをフルでお伝えすると最低3日はかかります。その時は、ご質問のような考え方も当然ご紹介しています。ですから、典型例をベースに『仕事のOS』と『マネジメントスペクトル』の考え方をみなさんで発展的に検討なさることをお勧めいたします。ご質問の答になりましたでしょうか。」 課長「はい、良くわかりました。典型例をベースに考えてみます。」 コンサルタント「不明点はいつでもお問い合わせ下さい。それでは、このシート(図4-3)のポイントをお話しましょう。それは、質と量にあります。仕事には質的要素と量的要素がコインの裏表のようにいつもありますよね。さきほどの主客のバランスみたいにね。どんな仕事にも、この質と量の要素がある訳です。ということは、その仕事をどう進めるかというプランニング、目標の設定にも、この質と量の要素が必要不可欠だということですね。」 「ということは、年間売上目標100億円!!なんていう目標は、ダメな目標ということでしょうか。」とある課長代理が質問した。 「いや、またしてもいい質問ですね。おっしゃるとおりです。100億円という量は明確ですが、質がわからない。これじゃ、どう具体的に動けばいいかわりませんよね。」 課長代理「そうなんです。年間予算はわかっても、それって量、数字じゃないですか。具体的な仕事に結びつかないっていうか、イメージできなくて困っていたんですよ。」 コンサルタント「質たとえば、既存顧客をベースにとか、新規開拓でとか、競合A社の切り崩しでとかの中味、質がわかって、量もわかれば、それを実現するための具体策、行動も明確にできますよね。そこが大切なポイントなんです。」 望月は、コンサルタントの話しを聞きながら、「やる気」のことを思い出していた。部下のやる気がないと嘆く前に、自分の目標設定なり、伝達方法に問題がなかったかどうか検討することのほうが先決問題なのだと感じていた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 アクションマネジメントとは?! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休み時間に、例のコンサルタントの前は黒山の人だかりとなってしまった。望月は、それを見て、しめしめと思ったが、次の瞬間、セミナー前のコンサルタントの言葉を思い出した。 「いやあ、望月さんのご要望ですから、何とか1日でまとめますが、本気でやるなら3日は必要ですよ。こちらも責任指導できますからね。企業によっては、半年かけてやるケースもありますから。」どうも、あの言葉は嘘ではなかったようだ。望月自身も、従来はさほど重要には思っていなかった仕事の進め方の知識が、これほど奥が深いものとは思ってもみなかった。また、奥が深くとも、ヘコたれずにヤルべき最重要課題であるとも思いはじめていた。 コンサルタント「休み時間にたくさんの質問がありましたが、このテーマはあせらずじっくりが肝要です。先は長いですから、腰を据えて取り組んでください。では、アクションマネジメントについて、かんがえてみましょう。」とコンサルタントは例によって1枚のOHPシートを取り出した。(図1−20)
望月「順調に行っていれば、この勉強会も、会議のプロジェクトもやってませんよ。予定通り、目標通り仕事が進まないので、困ってるわけですよ。」 コンサルタント「大変失礼しました。では、目標通り、予定通り仕事を進めるコツをご紹介しましょう。」 とコンサルタントはOHPシートの説明をはじめた。全員、我が身の問題なので真剣に聞き入っている。 コンサルタントの話しをまとめると、以下の通りであった。 1.仕事には事前にわかるものと、そうでないもの(突発)がある。 2.予定通り、目標通り仕事が進まないしくみは、この2つの仕事があるせいである。 3.100%、予定通り、目標通り仕事を進めることは、まず不可能と知れ。 4.その上で、いかに100%に近づけることができるか、または、予定通り、目標通り行かないことによるダメージをいかに少なく抑え込むことができるかを考えよ。 5.それを実現するためには、優先順位の発想は不可欠である。 6.その優先順位は「それが大事」と「何からやるか」の2つの意味がある。 と、いうことを学び、望月の部の仕事にあった具体的な優先順位のつけ方を伝授してもらった。(図1-20-b)
ということで、仕事のOS勉強会は大好評のうちに終了した。 参加者からは、「コロンブスの卵」だとか「目からウロコが落ちた。」とか、大変役に立ったようだ。 望月もセミナーを聞きながら、会議対策のいくつかのヒントが浮かんでいた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy Right (株)仕事の科学研究会