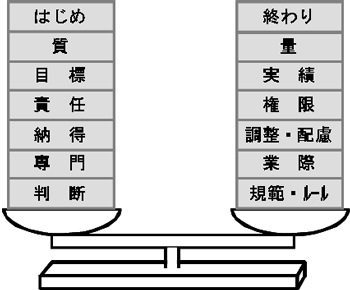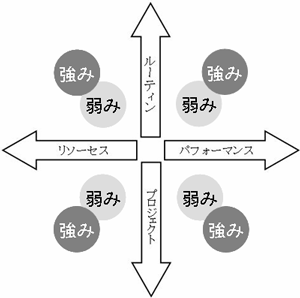| ■□■□ 第7時限 効果的で合理的に、仕事を進めるために ■□■□ | |||||||||||
| 49 「正しい意思決定」とは? 自分にしかコントロールできない、仕事の「はじめ」「質」「目標」などを重点的に考えて 意思決定することが肝心です。 つまり、自分の責任において意思決定することが大事です。 |
|||||||||||
| 人は、物事を決めるとき、一般的には、あれやこれやと悩みます。 悩み続けて、一生意思決定をしない人も実際たくさんいると思います。私はタイムマネジメントのコンサルタントで人生相談員ではありませんが、物事を決めるということは、事の大小の差があっても、人生そのものだと思っています。 人生が楽しいのは、物事を決める瞬間にあるように思います。 物事を良かれ悪しかれ決めるとスッキリするのも、これから新たな人生が始まると、心と体が期待するからかもしれないと思っています。 しかし、多くの人は、物事をそうすんなりとは決められません。いろいろなしがらみがあるのが人生です。もちろんビジネスの世界でも同じです。 「しがらみ」に登場してくるのは、「他人」です。他人のことが頭に浮かぶので、私たちは悩み、迷うのではないでしょうか?では、他人のことなど考えない、としたらどうなるでしょうか? 一般的には、わがままとか、偏屈とかいわれるかもしれません。 しかし、他人のことを考えるのは、とっても大事なことですが、ここでもやっぱり、「自分」と「他人」のバランスを考えると、「自分」がおろそかになりすぎているんじゃないかと思います。 そこで、本書の冒頭でご紹介した、「仕事のスペクトル」を思い出して下さい。 自分と他人のバランスで七つの要素に仕事を分けました。この七つの要素と、意思決定は密接に関係しています。それが下図です。 まずは、自分と他人とのバランスのなかで、自分にしかコントロールできない、「はじめ」「質」「目標」などを、重点的に考えて意思決定する。つまり、自分の責任において意思決定することです。これは正しい意思決定の方法だと思います。ポイントは次の七つです。 ①まずは、「いつから始めるか?いかに上手にやれるか、できるか」をチェック。 ②次に、「今の自分の力量を考えて、いかに上手にやれるか、できるか」をチェック。 ③さらには、「自分の到達したい目標は何か?」をチェック。 ④四番目は、「自分が果たすべき責任は何か?」をチェック。 ⑤五番目は、「自分自身が納得できる状況は?」をチェック。 ⑥六番目は、「自分の力の発揮できるところは何か?」をチェック。 ⑦そして最後に、「自分の力だけでやれる範囲」を考えて、意思決定する。 ちょっと多いかもしれませんが、意思決定は、人生の大事な行事と考えれば、これくらいは、やっておいたほうが良いでしょう。 この作業をして、仮に失敗したとしても、次の手が打てる余地ができます。武道でいうところの「残心」です。手を抜いた技には、残心はできませんが、全力の技には、必ず「残心(あとの備え)」ができる、とは武道の奥義書には、よく見られる表現です。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 50 「バランスのとれた意思決定」とは? 正しい意思決定も、修正を余儀なくされることがあります。 この正しい意思決定に修正を加えたものが、「バランスのとれた意思決定」であり、実現性は数段向上することになります。 |
|||||||||||
| 「正しい意思決定」とは、自分がコントロールすべきことを中心に考えた意思決定です。 人からは、自分勝手とか、わがままと誤解されるかもしれませんが、意思決定の土台となることなので、私は、「正しい」という言葉をつけることにしています。 しかし、実際の日常も、この意思決定だけで事が運べば、かぎりなく幸せですが、そうもいきません。 なぜなら、実際の日常には、「他人」という存在が必ずあるからです。 そこで、正しい意思決定も、修正を余儀なくされます。 この正しい意思決定に修正を加えたものが「バランスのとれた意思決定」です。 ただ修正を加えただけでは、「バランス」のとれたものにはなりません。そこで、再度、登場するのが、「仕事のスペクトル」です。 「正しい意思決定」が、自分がコントロールすべき七つの項目を中心に考えたものでした。それに、他人と共同でコントロールしなければならない対極の七つの項目を加味することで、「バランスのとれた意思決定」が実現します。 下図で具体的にみてみましょう。 「正しい意思決定」では、「はじめ」を考えましたが、「バランスのとれた意思決定」では、それに「終わり」を加味します。 これにより、投下時間がどれくらいか、どれくらいの時間で仕上げるかがわかってきます。 次は、「質(いかに上手に)」に対しては「量」です。どれくらい多くやるか、いかに多くやるか、こなすかを考えることです。 同様に「目標」(夢)に対して、「実績」(実現可能な状況)を考えることです。 「果たすべき責任」に対しては、「行なえる権限の範囲」を考えることです。 「納得するまで考える」に対しては、「相手への配慮、調整」を考えることです。 「得意分野で考える」に対しては、「自分と周りの接点(業際)」を考えることです。 「自分の力量で考える」に対しては、「ルールや規則を確認」しながら考える、ということになります。 こうすることにより、自分の主張を明確にしつつも、相手との接点を考えたバランスの良い意思決定が可能になります。 当然のことですが、「バランスのとれた意思決定」のほうが実現性は数段向上することになります。 なぜなら、周りの支持を得やすいからに他なりません。 いくら、力がある人でも、一人でやるのと、多少力はなくても、周りの支持をうけながら事を行なう人では、当然後者のほうが断然有利となります。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 51 意思決定のために「投下時間」を把握しよう 投下時間を読むことで目的意識も高まり集中できます。 投下時間の把握できる仕事と把握できない仕事があります。 後者も、どれくらいで仕上げるのかの予想と目標を立てて臨むことが大事です。 |
|||||||||||
| 効果的で合理的な仕事をするには、意思決定はたいへん重要です。 その意思決定の判断材料として、投下できる時間を把握する、ということが、全ての出発点といっても過言ではありません。 この節では、仕事の投下時間の把握について、考えてみましょう。 みなさんは、一つの仕事に取りかかる前に、その仕事がどれくらいの時間を要するか、考えてから仕事を進めていますか? または、どれくらいで終わらせようと目標を定めて取りかかっていますか? この作業をするのと、しないのとでは、大きな差が出ることをご存知ですか? 投下時間を読むことによって、目的意識も高まって集中できますから、短時間で終わったり、ミスが少なかったり、さらには、その作業自体がノウハウとなって、次回似たような仕事をするときには、もっと少ない時間でやれたりと、いいことずくめです。 しかし、仕事には、やってみないとわからない、というのも結構あります。 そのせいか、考えずに仕事に取りかかる傾向が私たちには顕著のような気がします。 そこで、仕事の種類と、投下時間の関係について、下図にしましたので、ご覧ください。 投下時間という切口で仕事をみると、二つの仕事に分類されます。 それは、「投下時間の把握できる仕事」と「投下時間の把握できない仕事」です。 「把握できる仕事」は、毎日、毎週、毎月、定期的にやっているルーティンワークや、過去にやったことのあるような経験のある仕事です。 これらの仕事は、おおよそ、どれくらいの時間が必要なのかの読みができます。読みができるのであれば、そこでもうひとふん張りしてみましょう。 それは、「今までよりも短時間」でやるということです。 これをしないと、投下時間の把握をしても何の意味もないということになります。スキルアップ、力をつけるための投下時間の把握だと認識してください。 「把握できない仕事」は、単発で行なうプロジェクトワークや、初めて行なうような仕事です。 これらの仕事は、過去の類似の仕事から投下時間の推測のできるものもありますが、多くは、やってみないとわからないということになります。 ここで大事なことは、そこで投げ出さず、仮に予定がズレてもしょうがないと割り切って、とりあえず、どれくらいの時間で仕上げるかの予想、目標を立てて臨むことが大事です。 そうすることによって、次回、似たような仕事が発生したときの、貴重なノウハウとなって、経験が蓄積されることになります。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 52 「理由」「目的」「動機」を把握しよう 仕事に対する「理由」「目的」「動機」の認識のズレが、マチマチな仕事につながっています。 今一度、仕事の「理由」「目的」「動機」を整理しておくことをおすすめします。 |
|||||||||||
| 一つひとつの仕事(コピーをとるような簡単な仕事から、企画書を作るような仕事まですべての仕事)には、必ず、「何のためにやるか?」とか、「なぜやるか?」の理由や目的があります。 しかし、日々の仕事のなかで、私たちは、それら一つひとつの仕事の理由や目的を考えて取り組むことは、まずありません。 どうしてでしょうか? 考えなくても、とりあえず仕事を仕上げることができるからだ、と私は考えています。 しかし、重大な局面を迎えると、このスタイルでは、立ち行かないことになります。 マクドナルドのプライスリストに「スマイル 無料」というのがありますが、その理由、目的を十分理解している従業員はどれだけいるのかなあ、と思ったりもします。 私は、あのプライスリストが好きです。 マックのはあまりお世話になりませんが、あのスマイルにコミュニケーション、特にお客様との接点における本質を見るような気がします。 スマイルのないところに、いいコミュニケーションは生れないのは、古今東西の真実だと思います。 ちょっと話は脱線しましたが、すべての仕事には、「理由」「目的」があって、その「理由」「目的」によって私たちの仕事は、大きな影響を受けることになります。 「理由」「目的」「動機」と呼ばれるものがはっきりしないと、「いかに上手にやるか(質」と「どれだけ多くやるか(量)」を定めるときに、方向性を見失うことにもなりかねません。 社内で、月一業務(業務清算など)を行なっても、人によってできがマチマチなことがよくあります。多くの場合、それは、各人のスキル(技術)の問題として片付けられていることと思います。 しかし、私は、その仕事に対する、「理由」「目的」の認識のズレが、マチマチな仕事につながっているんじゃないの?と、頭が回転してしまいます。 ある種の職業病かもしれませんが・・・。 「理由」「目的」「動機」の把握は、仕事を段取るとき、計画を立てるときの出発点ともいえる作業です。チームでの作業であれば、メンバー全員で意思統一しておくべき内容といえます。 下図のように、「理由」「目的」「動機」から、「いかに上手に」と「いかに多く」が導かれ、それは、仕事をする各人の思いと、仕事をする仲間同士の共通に理解しあえるような目標となっていきます。 いい換えるなら、そのようなプランニングをしないと、自分も活かせないし、他人も活かせないということになってしまいます。 大事な仕事だけでかまいませんから、今一度、「理由」「目的」「動機」を整理しておくことをおすすめします。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 53 優先順位の特性を把握しよう 優先順位は、究極的には一人ひとりの価値観と結びついており、一人ひとり優先順位は異なっているものです。 大事なことは、コミュニケーション等で、それらのバラバラを統一する作業です。 |
|||||||||||
| 効果的で合理的な仕事を進めるにあたって、優先順位の把握も欠かすことのできない重要ポイントです。 しかし、巷では、「優先順位が大事だ」とか「プライオリティが問題」とか、社内での議論でも頻繁に登場しますが、優先順位の性質について、知っている人はほとんどいないだろうな、と思っています。 つまりいくら声を大にして「ゆうせんじゅんい!」と叫んでも、響かないのは当たり前。言ってる人が、その「優先順位」をよく理解できていないことが多いわけですから。 そこで、優先順位について性質をまとめると下図のようになります。 優先順位は、時間の幅(単位)によって変わる性質があります。 もちろん、今日、今週、今月、今生(人生)の優先順位がすべて一致しているという人は、まれですが、いらっしゃいます。そんな人の行動は多分スキがありません。動きにもムダは一切ないだろうと思います。しかし、一般的には、この時間の幅によって、優先順位が変化します。 大事なことは、時間の幅によって異なる優先順位を一致させることではなく、それぞれによって違う優先順位を明確にすることです。 時間の幅で、優先順位は変わりますが、時間の幅が少なくなればなるほど、重要性よりも緊張性という優先順位もどきに、足を引っぱられることになります。これの防御策は、緊急性ではない、重要性での明確な優先順位を常に把握しておくことしかありません。 なぜなら、緊急性の代表的なものは突発の仕事です。いつ、なんどきやってくるか分かりません。これに対抗するには、一日単位の優先順位だけでも明確にしておく必要があります。 よくこんな場面に出くわします。 会議で、「これが大事ということで、本日は有意義でした」、なんて会議が終わり、参加したメンバーの誰もが、その大事を、会議が終わってから着手しないということがあります。これも優先順位の性格をあらわしているできごとです。 優先順位には「これが大事」という意味と、「これから始める」の二つの意味があります。「パレートの二割八割の法則」を仕事に活かそうと思ったら、この二つの意味を一つにまとめる必要があります。 つまり、頭で思っている「これが大事」と、手足が行なう、「まずこれをやろう」が一致しないと、意味がない、ということです。 最後は、優先順位は、究極的には、一人ひとりの価値観と結びついています。つまり、一人ひとり優先順位は異なっているのが正常だということです。 大事なことは、コミュニケーション等で、バラバラを統一する作業です。 これを怠ると、仕事にならなくなります。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 54 人材を把握しよう 仕事を効果的で合理的に進めるためには、仕事仲間の力量を知ることは仕事の成否に直結します。 まず最初のチェックポイントは、「顔に力がある人」―顔の表情筋の豊かな人です。 |
|||||||||||
| 「顔に力がある人」「表情豊かに聞ける人」「話せる人」は、コミュニケーションの力もあります。 効果的で合理的に仕事を進めるためには、仕事仲間の力量を知ることは、仕事の成否に直結する重要な問題です。 なにしろ仕事のは一人ではできませんから、仕事仲間の力の良し悪しは、仕事の成果を左右することになります。 私も様々な企業や団体さんの中に入って一緒に仕事をさせていただく機会は非常に多いですが、「仕事の科学研究会」の社員や「NPO法人日本タイムマネジメント普及協会」の職員との仕事も多くあります。今までに、幾度となく、人の採用では、失敗を繰り返して来ました。 後述のチャックポイント以前の問題で結構つまずきました。 そして、現在、到達しているのが、「顔に力がある人」という判断基準です。 「顔に力がない」と一緒に仕事をしても長続きはできないという、苦い経験の産物です。 ちょっと科学的にいえば、顔の表情筋の豊かな人ということになるでしょうか。 この手の人は反応が分かりますから、まずコミュニケーションが十分とれます。無反応な人とのコミュニケーションは苦痛以外の何物でもありません。 ですから、上手に話す、上手に聞く前に、表情豊かに聞ける人、話せる人は、コミュニケーションの力もあると思います。これが、まず最初のチェックポイントです。 次は、仕事の進め方の技術です。 本書でご紹介した各種のスキルをどこまで実現できているかというポイントです。 しかし、これらのスキルを最初から身につけていることはほとんどありません。後から考えて、それを自分のものとして、日々実現しているか、どうかということだと思います。 ここでのポイントは、「自分一人で行なう仕事のはじめ」のコントロールができているかどうか、ということになると思います。これができている人は、間違いなく、主体的で創造的で、責任感も強い人だと私は思っています。 最後は、専門的な知識、技術です。 このチェックポイントは、失敗はOKだが、二度と同じ失敗はしない、という点です。 多くの人は、これができていません。つまり、せっかくのチャンスだった失敗を自分のものとしていないということですから、この手の人に命を預けるのは避けたいものです。 以上、各人のチェックポイントをお話しましたが、人間は環境に左右される動物でもあります。その意味では、下図のように、「コミュニケーション」「仕事の進め方」「専門知識」の三つの分野において、企業のルールや環境整備がどうかもチェックしておいたほうがよいでしょう。 もし、問題があれば、人の問題ではなく、組織、チームの問題で成果が出しづらい状況になっている可能性が大です。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 55 自分自身を把握しよう 私たちが一番不得手としているのは、実は己を知ることです。 仕事のジャンル別の自分の「強み」「弱み」を把握するだけでも、「自分という存在」が見えて来ます。 |
|||||||||||
| 孫子の兵法にもあるように、「己を知り、的を知れば百戦危うからず」です。 しかし、私たちが一番不特手としているのは、実は、己を知ることです。 リサーチ会社に多額の費用を払って市場調査(敵を知る)をしても、自社の商品なり、自社の調査が不充分で、まとはずれなプロモーション計画というのは、日本中に転がっています。 ここでも、「自分」と「他人」という点でいえば、「自分」への重点の置き方が足りないということでしょうか。 さて、下図は、そんな自分を把握するのが苦手な人のために、分かりやすく自分をチェックするやめのマトリックスです。 「仕事の科学研究会」では、このマトリックスをベースにした、投下時間の調査も行なっています。いろいろな会社で、企業変革の際の貴重な、役立つデータを提供させていただいています。 仕事は、目的で考えると、「パフォーマンス」(売上など対外活動)と「リソーセス」(人材活動など内向活動)の二つしかありません。 また、取り組み方で考えると、「ルーティン」(日々恒常的に行なう)と「プロジェクト」(期間限定で行なう)の二つしかありません。 この二つの軸をかけあわせて、四つのジャンル別の投下時間の割合や、それぞれのジャンル別の自分の強み、弱みを把握するだけで、「自分というものの存在」が見えて来ます。 また、現状で生じている問題の原因も分かるかもしれません。 一度、時間を見つけて、取り組んでみてください。きっと新たな、驚くような事実に気がつくことと思います。 このマトリックスで、自分の「強み」と「弱み」が分かったら、次に何をするかを考えてみましょう。 四つの分野のそれぞれ、「強み」と「弱み」で合計8項目になると思います。 これから目指すべき方向などを考えて、最優先で取り組みべき項目を決めてください。 留意点としては、調子の良いときは弱みの改善を、調子の悪いときは強みの伸展を、さらに強くする方向の取り組みをするほうがよいでしょう。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 56 「思うがまま」に仕事をする方法とは? 自分自身やりたいこと=目標を具体的にしたうえで、まわりの人に上手に説明して理解を得る事です。 そうすればまわりの人の貢献で、思い通り、予定通りに仕事は進んでいきます。 |
|||||||||||
| 「思うがまま」に仕事ができれな、この上ない幸せです。思い通り、予定通りに仕事が進み、やりたいことが確実に処理されていくのは、みなさんも望むところでしょう。 みなさんもビジネス経験の中で、そんなラッキーな日の経験は何回かあると思います。 そんな日の特徴は、自分の力でそうなったかというと、そうではありません。まわりの人たちの予期せぬ貢献で、思ったことが次々と実現したということではないでしょうか? つまり、自分も努力はしているが、それと同等かそれ以上にまわりが動いてくれたので、思い通り、予定通り仕事がはかどったということだと思います。 「思うがまま」に仕事をするとは、決してわがままにマイペースで仕事を好き勝手にやることではないと思っています。いかに、まわりが動いてくれるかがポイントではないでしょうか? 別の表現をすれば、あなたのやろうとしている仕事、やっている仕事に対し、まわりの人たちがどれほど支持してくれているかが、「思うがまま」の測定バロメーターといえます。 極論すれば、「思うがまま」に仕事ができないのは、まわりの指示がないからといえそうです。 こう考えてくると、本書で、ご説明した内容は、すべて、この「思うがまま」につながっていると、理解いただけるでしょうか? 少なくとも、著者としては、「思うがまま」の仕事を実現するために、色々な考え方や様々なスキル、ハウツーを本書でご紹介させていただいたつもりです。 これは、あくまでも私の「つもり(主観)」なので、つもりを実現(客観)にするのは、読者の皆様(もちろん私も含めて)の今後の動きにすべてがかかっているといってもいいと思います。 「思うがまま」の仕事は、思う本人である自分自身がはっきりしないと実現しません。自分のやりたいこと、やろうとしていることがどれだけ具体的になっているかがポイントです。 次に、仕事を、いかにまわりの人たちに上手に説明(コミュニケーション)し、理解を得、協力してもらうか(または、仕事の一部をやってもらうか)も重要です。 そして、まわりが上手に動いてくれないとき、「アイツ」が悪いと相手を責めるのではなく、自分はまだ、「支持」されていない現実を直視し、どうすれば、もっと動いてくれるかの対策(自責)をとることです。 本書の第1時限から第7時限までの内容のゴールは、「思うがまま」です。 第1時限からの内容を振り返り、自分のものとして、「思うがまま」の仕事に、少しでも近づけるよう励んでください。私も、協力させていただきます。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Copyright(C) The Association of Japan Time Management Popularization. All Rights Reserved.